会社経営の失敗を防ぐ失敗経営学|ピンチはチャンスの始まり
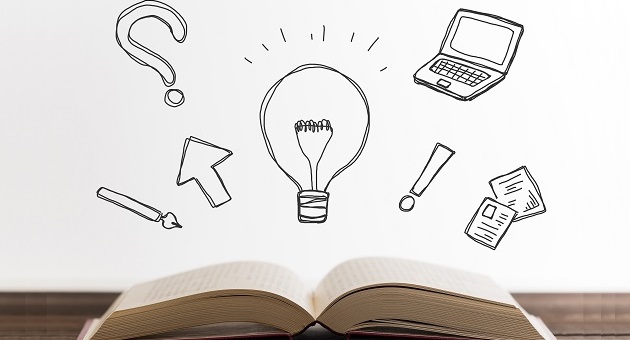
失敗は必然の結果なので、失敗を活かす経営姿勢は成功の糧になる。
また、成功は失敗のない連続性で形作られるので、失敗に対する感度が高いほど、成功のチャンスが広がる。
この記事では、会社経営の失敗を防ぐ失敗経営学について、詳しく解説する。
成功事例は役立たない!?

経営ノウハウに関連する情報世界を見渡すと成功事例をもとにした方法論で溢れている。
また、成功する方法から何かを学ぶ姿勢が当たり前のこととして世間に受け容れられているためか、多くの経営者も成功から学ぶことに対して何の疑問も抱いていない。
ビジネスの多様化は加速度的に進んでいる。
中小企業も多様化の例外ではなく、成功の論理、或いは、安定経営の論理は企業の数ほど存在する。
会社ごとにヒト、モノ、カネ、情報等の経営資源に大きな差がある中小企業において、共通の成功論理など、最早、存在しないだろう。
何れにしても、ある一つの成功事例が全ての会社に当てはまる時代は、とうの昔に過ぎ去っている。
それにも関わらず、脚光を浴びるのは未だに成功事例ばかりだ。
冷静に考えてほしい。
成功事例ばかりを学んだ経営者に、
▶失敗を乗り越える知恵があるだろうか?
▶小さな失敗をかわす知恵があるだろうか?
マイクロソフト社創業者で大富豪のビル・ゲイツ氏も「成功は最低の教師だ」と語っているが、実は、中小企業の安定経営に成功事例が役立つことは殆どない。
失敗事例は非常に役立つ

成功事例に比べて、失敗事例は非常に役立つ。
なぜなら、成功(安定経営)を支えるのは、失敗のない連続性だからだ。
資本力が乏しく、少しの判断ミスで経営が悪化するリスクを抱えている中小企業にとって、失敗事例ほど役立つものはなく、失敗を活かす経営者の姿勢が、安定経営、しいては、成功の礎を作るのだ。
約三百年に亘り天下を治めた徳川幕府を築いた徳川家康は、織田信長、豊臣秀吉等、時代を共にした武将の失敗事例を徹底的に学び、成功の礎を作った。
天下の剣術家であった宮本武蔵が追求した剣は、勝負に勝つ剣ではなく、勝負に負けない剣だった。
日本のプロ野球界で選手・監督として活躍した野村克也氏は「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という肥前平戸藩主・松浦静山の名言を引用して失敗の理を語った。
会社経営も同じである。
成功は偶然の産物であり、失敗は必然の産物と云われるように、失敗には法則があり、失敗するべくして失敗すると云われるほど、失敗から学べることが沢山ある。
事実、失敗から何かを学んで経営している社長と、そうではない社長では、会社の業績に天と地の開きがでる。
失敗のメカニズムとは?

失敗事例が安定経営に役立つ理由は、失敗のメカニズムが分かれば理解できる。
失敗のメカニズムは簡単だ。
経営者も、社員も、人は必ず失敗を犯す。そして、失敗には必ず「失敗の芽」が存在する。
失敗の芽が小さければ会社経営に与えるダメージは小さく済むが、失敗の芽がそのまま放置されると、会社経営に大きなダメージを与えるリスクに繋がる。
つまり、事前に小さな失敗の芽を摘むことさえできていれば、会社経営が傾くほどのダメージが生じることはないということだ。
失敗は確率現象でもあるので、ハインリッヒの法則(1:29:300の法則)で説明することもできる。
ハインリッヒの法則とは、1件の重大事故の陰には29件の軽度事故があり、更にその陰には300件のヒヤリとした事故があるという法則である。
この法則に失敗を当てはめて考えると、300件のヒヤリとする失敗の芽を摘み続けている限りは、29件の小さな失敗も、会社経営に大きなダメージを与える1件の大きな失敗(不祥事)も起こり得ない、ということがいえる。
これが、失敗のメカニズムであり、安定経営を支える失敗のない連続性を支える仕組みである。
失敗は「失敗の芽」であると同時に「成功の芽」でもある。
失敗をネガティブに捉える必要はなく、むしろ、失敗をポジティブに捉えた方が、成功の芽を発掘しやすく、安定経営の基盤が整い易くなる。
失敗は成功(チャンス)の始まり

果たして、中小企業経営者の中で失敗と向き合っている方はどの程度いるだろうか?
そもそも、成功事例は様々な形態で世に語り継がれていくが、失敗事例が記録される習慣は殆どない。
どんなに大きな不祥事であっても会社経営の失敗事例が貴重な経営資源として活用されることは稀だ。
ましてや違う会社の失敗事例を記録で残している会社など皆無といっていいだろう。
また、元来失敗というのは、見たくない、忘れたいという心理が自然と働くので、3の法則の通り、3日、3週間、3ヵ月と経過すると共に殆ど忘れ去られる運命にある。
新聞報道等で大々的に報じられる企業経営の失敗(不祥事)が、世間の記憶から次第に遠のくのは、こうした自然作用が働いている。
しかし、「失敗は成功のもと」といわれる通り、失敗事例ほど会社経営に役立つものはない。
失敗事例は成功事例とは違い、どんな会社にも当てはまる教訓として有効に活かすことができるからだ。
何故、失敗したのか?
そして、失敗を防ぐにはどうしたら良いのか?
経営者自身が大きな失敗を経験する必要はない。
他人の失敗に学ぶ姿勢ひとつで、成功のチャンスをいかようにも見つけ出すことができるのだ。
安定経営は失敗のない連続性を確立することで築くことができます。その為には、経営に客観性を持たせることと経営者が謙虚であり続けることが不可欠です。客観性と謙虚さがあれば、敏感に失敗を感知することができますので、自然と失敗の芽を摘むことができます。先手先手で失敗の芽を摘むことが安定経営の原則なのです。

























