資産診断で分かる会社の問題点|資産診断で会社の衰退リスクを払しょくする

会社の資産診断は最低でも毎月1回は必要だ。
なぜなら、資産診断で会社の問題点を捉えることが出来れば、会社の衰退リスクが小さくなるからだ。
この記事では、資産診断で分かる会社の問題点と、その問題点の深刻度を測定する資産診断手法について、詳しく解説する。
資産診断で分かる会社の問題点
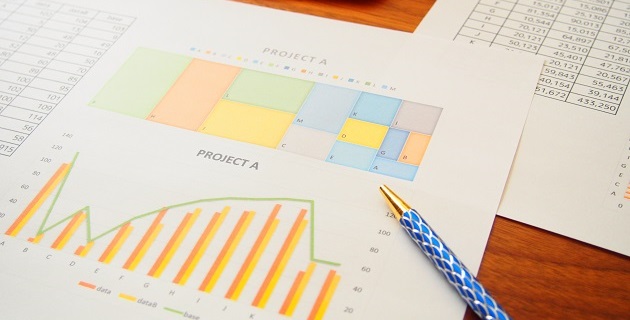
会社の資産診断の根拠資料は貸借対照表を用いるが、資産診断を通じて分かる会社の問題点は「資本効率・支払能力・安全性」の3項目になる。
この3項目の資産診断結果が良ければ衰退リスクは低く、逆に、この3項目の資産診断結果が悪ければ衰退リスクが高いといえる。
つまり、「資本効率・支払能力・安全性」の適正度合いが分かれば、衰退リスクを上手にコントロールすることが出来るのだ。
資産診断をするうえで重要なポイントは「資産の診断方法」と「診断の結果判定」である。
当然ながら、資産の診断方法を誤れば、正しい診断結果は出ない。更に、資産の診断方法が正しくても、診断の結果判定を誤れば、同様に正しい診断結果は出ない。
誤った診断結果をもとに経営改善を行っても、成果が出ないであろうことは容易に想像できるだろう。
問題点を明らかにする資産診断方法

正しい資産の診断方法と結果判定基準を習得することが、正しい資産診断結果を導く条件であり、正しい資産診断結果は経営改善の目標を明確にし、安定経営の実現に貢献する。
安定経営の実現に欠かせない「資本効率・支払能力・安全性」、この3項目の問題点を明らかにする資産診断の具体的方法は下記の通りになる。
資産診断で分かる「資本効率」の問題点
資本効率の適正診断(問題点)は「総資本回転率(売上高(年商)÷総資本)」で分かる。総資本回転率とは、資本効率を計る経営指標のことで、例えば、会社設立時点の資本は、資本金である現金しかないが、会社経営が始まると商売を通じて資本(現金残高)が大きくなる。
少ない資本で大きな売上が獲得できれば、経営の資本効率が高いといえるが、概ね、1回転以上が標準水準になる。但し、設備投資が多く固定資産の比率が高い業種業態と、設備投資が少なく固定資産の比率が低い業種業態では標準水準に差があるので、その点は留意してほしい。
なお、標準水準を下回っている場合は、次のような問題点が考えられる。
・投じた資本の割に売上が伸びていない
・資産の中に、不良性の資産が含まれている(例えば、遊休資産、不良性の売掛金、水増し在庫等々)
資産診断で分かる「支払能力」の問題点
支払能力の適正診断(問題点)は、「当座比率〔(当座資産÷流動負債)×100〕」で分かる。当座比率とは、支払能力を計る経営指標のことで、例えば、当座資産よりも流動負債が大きく下回っていれば支払能力が高く、当座資産よりも流動負債が大きく上回っていれば支払能力が低いと判断できる。
概ね、90%~119%が標準水準になり、標準水準を下回っている場合は、次のような問題点が考えられる。
・赤字経営に陥っている
・過剰投資を行っている
・借入金過多に陥っている
資産診断で分かる「安全性」の問題点
安全性の適正診断(問題点)は、「自己資本比率〔(自己資本÷総資本)×100〕」で分かる。自己資本比率とは、会社の資本力や安定経営の度合を計る経営指標で、例えば、返済義務のある他人資本よりも自己資本の方が上回っていれば会社の安全性が高いと判断できる。
概ね、20%以上が標準水準で、40%以上だと優良水準になる。標準水準を下回っている場合は、次のような問題点が考えられる。
・赤字経営に陥り、年々自己資本が減少している
・借入金を中心に設備投資を行い、年々自己資本が減少している
資産診断の要点は「資本効率・支払能力・安全性」

資産の適正診断をする方法は様々あるが、この記事で解説した「資本効率・支払能力・安全性」、この3項目の適正具合いを常に把握していれば、会社経営に失敗するリスクが小さくなる。
貸借対照表に対して苦手意識を持っている中小企業経営者は少なくないが、貸借対照表は資産診断のみならず、会社経営の様々な局面で活用できる。
安定経営を確立したい経営者は、資産診断スキルと共に貸借対照表を読み解くスキルもしっかり磨くことをお薦めする。

























