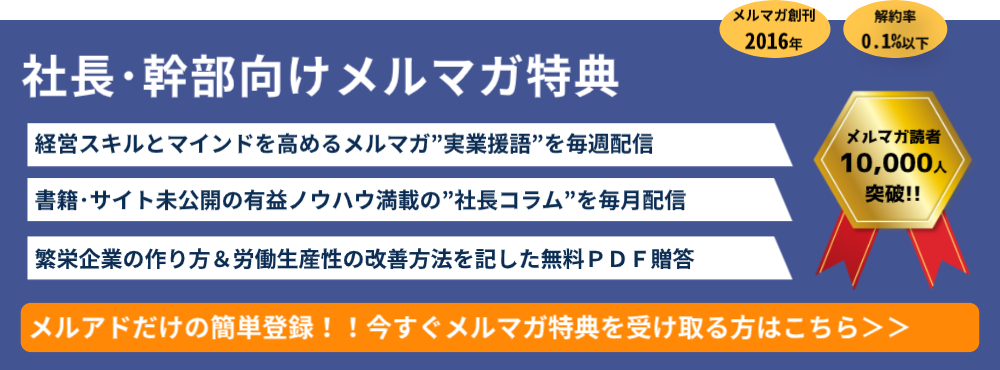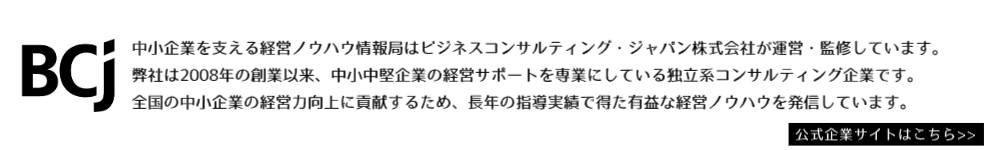役員報酬で税金をコントロールすることはできない|税金と役員報酬の密接な関係性とは

役員報酬で税金をコントロールすることは殆どできない。
なぜなら、定期同額支給以外の役員報酬は、原則、経費として認められていないからだ。
この記事では、役員報酬で税金をコントロールすることはできない理由、並びに、税金と役員報酬の密接な関係性について、詳しく解説する。
役員報酬で税金をコントロールすることはできない

定期同額支給以外の役員報酬は、原則、経費として認められていないため、役員報酬で税金をコントロールすることはできない。
例えば、利益を圧縮するために期中で役員報酬を増額しても、その増額分は経費として認められないため、税金を減らすことはできない。
むしろ、期中で増額した役員報酬相当分に法人税が課せられるため、税金を減らすメリットは全くない。
また、不当に高額な役員報酬や事実を隠蔽又は仮装して経理処理した役員報酬も、経費として認められていない。
さらに、上場企業では一般的な業績連動の役員報酬も、同族会社(殆どの中小企業が該当)には認められていない。
このように、恣意的な税金操作ができないように、役員報酬の取り扱いには厳重なルールが敷かれている。
なお、役員報酬の支給額を変更する場合は、株主総会の決議を経て、期首から3ヵ月以内に変更しなければならない。
決議もれ、変更期日切れの場合は、増加分の役員報酬が経費として認められないため、注意してほしい。
高額な役員報酬の上限は一体いくらなのか?

経営者の関心事は、高額な役員報酬の上限は一体いくらなのか、という点にあると思うが、これに関しても税法で取り決めがされている。
ひとつは実質基準で「役員報酬のうち、その役員の職務内容、その法人の収益、社員の給与状況、同業他社の役員報酬状況等に照らして、不相当に高額な部分の金額」という基準。
もう一つは形式基準で「役員報酬が定款の規定、或いは株主総会などで決めた役員報酬限度額を超える部分の金額」という基準である。
この実質基準と形式基準のいずれか多い金額が、基準超過分として経費として認められないことになっている。
とはいっても、この基準は、高額な役員報酬を制限するにはじつに曖昧である。
裏を返せば、定款や株主総会で役員報酬の上限額を決議することは必須だが、合理的基準さえあれば、高額な役員報酬は認められる余地があるということである。
例えば、前期の当期利益と役員報酬を合算した金額の〇%を役員報酬にするといった、その会社の収益の実態に合わせた実質基準に基づいて支給される役員報酬は合理性が高いといえる。
役員報酬と税金の関係

役員報酬には所得税が課せられる。
役員報酬に課せられる所得税は累進課税で最大税率は45%である。つまり、役員報酬の金額が多いほど、税金の税率が高くなるということだ。
なお、役員報酬の金額に応じた所得税率は下表の通りである。
|
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
|---|---|---|
|
195万円以下 |
5% |
0円 |
|
195万円超え 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
|
330万円超え 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
|
695万円超え 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
|
900万円超え 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
|
1,800万円超え 4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
|
4,000万円超え |
45% |
4,796,000円 |
(2019年4月時点の所得税率表)
ご覧の通り、役員報酬の課税所得が1,800万円を超えると、中小企業の実効法人税よりも税負担が重くなる。
多くの中小企業はオーナー兼社長というケースが多いと思うが、支払う税金を抑えて会社に財産を増やすか、或いは、多少の税金を払って個人財産を増やすかは、ひとつの選択ポイントになる。
例えば、役員報酬を抑えて会社の利益を出し、会社の財産を増やすことを優先すれば、会社の自己資本が増強されるので経営の安定感が増す。
逆に、会社の利益を極限まで減らして役員報酬を最大限に引き上げれば、税金の負担は重くなるが、自由に使える個人財産(お金)が潤沢になる。
どちらを選択するかは経営者の自由だが、わたしの考えは、会社の収益が突き抜けるレベルに達するまでは会社の成長を優先し、節税を考えながら役員報酬をコントロールするのが最も賢い方法ではないかと思っている。