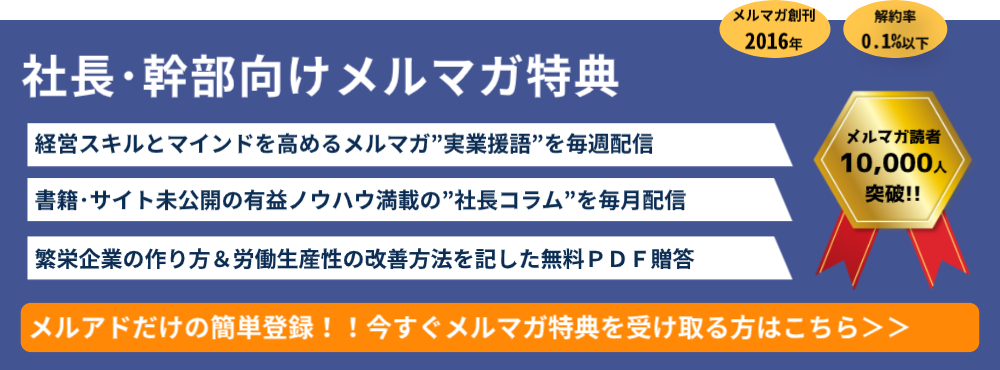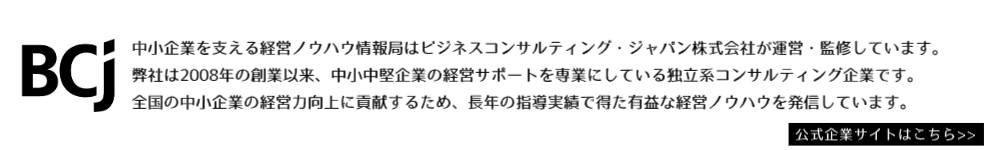事業繁栄の条件と法則|延命から永続性への転換のカギ

事業繁栄の条件と法則は簡単である。
一時しのぎや対処療法的な延命措置に終始せず、永続性に軸足を置いた経営采配を愚直に実践し続けることである。
この記事では、事業繁栄の条件と法則、並びに、延命から永続性への転換のカギとなる経営姿勢について、詳しく解説する。
事業繁栄の条件と法則

事業繁栄の法則は、一時しのぎや対処療法的な延命措置に終始しない、永続性に重きを置いた経営姿勢が基本条件になる。
倒産リスクが高まった企業に対して行われるつなぎ融資などは延命措置の典型になるが、こうした対応は事業繁栄の基礎を築く根本解決にはならない。
やはり、根本的な経営課題に対して愚直に向き合う経営姿勢が事業繁栄の基本原則であり、この姿勢が強固であるほど、事業の永続性が高まり繁栄が長続きする。
また、一時の好業績や、不調からのV字回復も油断や慢心からすぐに衰退に転じることは珍しくない。従って、どんな経営状況であっても、課題を見逃さない謙虚さも繁栄の絶対条件になる。
V字回復よりも大切なこと

わたしは2008年に経営コンサル会社を創業したが、創業当初は、経営コンサルのイロハを教えて下さったお師匠様とタッグを組んで、瀕死の企業を救う事業再建の仕事を数多くこなしていた。
会社倒産という最大の不幸を回避する仕事だったので、社会的意義も大きいと思い、大いにやりがいを感じて仕事に没頭していたが、ある日、お師匠様が仕事仲間から「あなたのやっていることは延命措置に過ぎない」と言われている場面に遭遇した。
正直、愕然としたが、冷静に考えると、一旦はV字回復(黒字化)に成功していながら、我々が経営から手を引いた途端に業績が悪化する会社は無きにしも非ずだ。
延命措置という指摘は、遠からず当たっていたので、喉に刺さった小骨のようにずっと心に引っ掛かっていた。
それからというもの、どうすれば自立的繁栄が確立できるかを模索し続けた。一時のV字回復ではなく、次世代に向かって光り輝く企業をいかにして創るか…。
達磨大師の面壁九年ではないが、自分なりの答えが見つかるまで、9年の歳月を要した。辿りついた答えは、型にはめないこと、依存させないこと、その先の未来を意識することである。
事業繁栄を後押しする経営姿勢

私が考えた末にたどり着いた、事業繁栄を後押しする経営姿勢の一端を紹介する。
まず、型を捨てた。経営サポートはいつも空っぽで臨み、実際に、社長とお会いし、会社を見学し、社員の皆さまとお話し、企業文化や歴史、提供商品やサービス、社長や働く方々の個性、市場や顧客等々を深く理解したうえで、その会社に最もフィットするオンリーワンの成長プランを考えるようにした。
次に、依存させることをやめた。社長が自立的に成長し続けられるように、サポート役に徹し、全身全霊で支える。経営判断においても、一切指図することなく、数パターンの選択肢を提案し、必ず社長に決断してもらうようにした。
最後に、その先の未来を意識するようにした。常に自分の経営サポートが無くなった後の未来を考えて、経営者に必要なスキルやマインドを先手先手で惜しみなく与え、自分の役割りが終わった時が、その会社(社長)の新たな成長ステージの始まりと思い、とにかく成功のピースを与え続けるようにした。
このスタンスで経営サポートすれば延命措置にはならないだろうと思い、満を持してお師匠様とのタッグを解消して独り立ちしたのが2016年である。
事業の繁栄は社長の自立が基礎になる

私の経営サポートは「社長の自立的な成長が繁栄の基礎になる」という考えが肝になっている。
実際に、経営サポートからちょうど一年が経過した時に、ある会社の社長さんから届いたメッセージを紹介する。
―以下メッセージ―
伊藤様、お世話になります。
一年前は八方塞がりのような状態でしたが、組織も業績も大幅に改善されました。私の感覚的には、会社が生まれ変わり視界が晴れたような感じです。それほど変わりました。
また、この一年での学びは自分自身や社員の成長に繋がりました。我々が短期間でここまで変われたのも、伊藤さんが親身になり熱心に指導をして頂いたお陰です、感謝しています。
今の経営体制であれば、大きな不安を抱えることなくこのまま邁進できます。引き続き、経営改善を止めることなく活動をしていきます。
―おわり―
如何だろうか。
社長の自立的成長と共に事業が繁栄している感じが伝わってきたのではないだろうか。
実は、前章で解説した、型を捨てる、依存させない、その先の未来を意識することは、会社を繁栄させる上でとても大切な感覚になる。
社長やリーダーがこの感覚を持っていれば、部下も会社も必ず成長する。そして、それらの成長は、回りまわって自分の成長に繋がる。
自分の正しさに執着したり、一時の報酬に執着したり、或いは、今だけ良ければそれで良しという思考では、何事も発展することはなく、場合によっては延命で終わる。
繁栄の基礎は、表層的ではなく、深層的・本質的な部分に寄り添うことで見えてくる。今の動きが延命措置に陥っていないか否か、折にふれてチェックすることをお薦めする。