中小企業の収益性分析と経営診断方法|企業の収益性は重要な診断ポイント

企業の収益性分析は、重要な経営診断の一つといえる。
企業の収益性が分かれば、成長投資の資金余力が分かり将来の投資戦略が自ずと見えてくるからだ。
この記事では、中小企業の収益性分析と経営診断方法について、詳しく解説する。
企業の収益性分析・診断の必要性

収益性分析は、中小企業の安定経営を実現するうえで欠かせない経営診断になる。
なぜなら、経営資源が脆弱な中小企業ほど、高い収益性なくして、会社の成長はあり得ないからだ。
企業の収益性が分かれば、成長投資の資金余力が分かり将来の投資戦略が自ずと見えてくる。また、適正な収益性を把握することで過剰投資等の経営判断の誤りを未然に防ぐこともできる。
更に、企業の収益性が適正指標よりも劣っていれば収益性を向上させるための対策を検討することができるし、適正指標よりも優れていれば収益性を維持するための対策を検討することができる。
会社経営は、闇雲に管理するよりも、正しい経営指標と目標を持って管理した方が数倍、経営効率が向上する。そのためにも正しい経営診断を行うことが重要になる。
企業の収益性分析・診断の具体的方法

中小企業の収益性分析と経営診断は、「売上総利益高営業利益率」と「付加価値金額」、この2つの経営指標を使って診断する。
売上総利益高営業利益率は、売上総利益に占める営業利益の構成比率、つまり、会社の収益性の高さを示す経営指標で、付加価値金額は、会社の可処分所得金額の大きさ、つまり、会社の収益量の大きさ示す経営指標になる。
会社の収益性は、利益率を上げるだけでは心もとなく、やはり、高い利益率に加えて、利益額の拡大なくして、会社の収益性は改善しない。
売上総利益高営業利益率と付加価値金額の2つの経営指標を用いた、中小企業の収益性分析と経営診断方法を順を追って解説する。
売上総利益高営業利益率の分析・診断方法
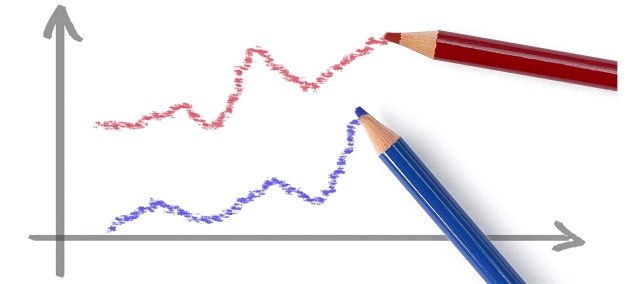
売上総利益高営業利益率は、売上総利益に占める営業利益の構成比率、つまり、会社の収益性の高さを示す経営指標で、業種業態関係なく、会社の収益性の適正判定ができる経営指標である。
売上総利益高営業利益率の計算式、並びに、診断方法は下記の通りである。
売上総利益高営業利益率=(営業利益÷売上総利益)×100
|
営業利益率 |
診断結果 |
|---|---|
|
11~20% |
優良水準である。会社の収益性が高く、持続的な会社成長が期待できる。 |
|
10% |
標準的な利益水準(収益性)である。 |
|
0~9% |
改善の余地がある。少しのきっかけで収益性が低下し、経営が低迷する可能性がある。 |
|
マイナス |
危険水準である。収益性の高低以前に、収益性がマイナスの状態である。赤字経営なので、早急に黒字化する必要がある。 |
|
20%超 |
危険水準である。儲かりすぎである。人件費の水準が低すぎないか?保守修繕に不足がないか?等々、会社の内部に歪みが出ていないか確認する必要がある。会社の内部に歪みがあると、内部から会社経営が崩壊していく可能性がある。特段問題なければ、この水準でも問題ない。 |
付加価値金額の分析・診断方法

付加価値金額は、会社の可処分所得金額の大きさ、つまり、会社の収益量の大きさ示す経営指標で、付加価値金額の計算式、並びに、診断方法は下記の通りである。
付加価値金額=総人件費+営業利益額
|
付加 価値 |
診断結果 |
|---|---|
|
増加 |
収益性が高く、良好な状況である。会社の利益と社員の報酬が増加に向かっている。 |
|
減少 |
収益性が低く、危険な状況である。会社の利益と社員の報酬が減少に向かっている。会社経営のなかにムダムラがないか徹底的に分析し、経営改善を行う必要がある。 |
企業の収益性は売上総利益高営業利益率と付加価値金額で分かる

中小企業の収益性は、利益率だけでは判断を誤る。
なぜなら、利益率が適正水準であっても、利益金額を含めた付加価値が増加傾向にないと、会社の成長スピードが鈍化するからだ。
従って、中小企業の収益性を診断する際は、必ず利益率と利益金額をセットに考えなければならない。
「売上総利益高営業利益率」と「付加価値金額」の両面で企業の収益性を診断すると、本当の姿が見えてくる。
収益性は会社の稼ぐ力だけでなく、競争力も示します。ですから、収益性を診断し、然るべき目標に向かって現状改善を推進すると自ずと競争力の高い企業体質に変貌します。また、収益性に意識を向けると、会社全体の利益意識が高まり、ムダやムラのない働き方が定着しやすくなります。





























